どうしたらむし歯にならないの? 
どうしたらむし歯にならないの?
ご飯やお菓子を食べると"食べかす"がお口の中に残ります。
"食べかす"はむし歯菌(ミュータンス菌・ラクトバチルス菌)によって"歯垢(しこう)"に変わります。
歯垢はむし歯菌の住みかです。その中でどんどん繁殖していきます。
歯垢はネバネバしていて水には溶けません。歯磨きしか取る方法はないのです。
歯磨きをせずに食べ続けていると…どんどんむし歯菌は増え、人の"食べかす"を食べて、むし歯の原因である"酸"を作り出します。
この"酸"が歯を溶かして穴を開け、「しみる」「痛い」むし歯になってしまうのです。
●唾液ってすごいんです。
唾液には3つの力があります。
① お口の中の酸を中和し正常な状態にする。
② お口の中を清潔に保ち、歯の表面を強くするなどの殺菌・抗菌・保護という作用がある。
③ 唾液には歯の成分であるカルシウムやリンが含まれており、歯にミネラルの補給をする効果がある。
キシリトールガムやスルメなどの硬いものを噛むと、唾液の分泌が促されます。
どんどん噛みましょう♪
●正しいブラッシングで1本の歯に対して20回磨きましょう。
歯磨きは、夜、おやすみ前に、頑張りましょう。
睡眠中は、唾液の分泌が少なくなり、むし歯菌が増えやすくなるのです。
睡眠中にむし歯菌を増やさない事が大切です。
●規則正しい食事を心がけましょう。食事の回数と時間を決めて食べましょう。
むし歯を予防するには、正しい食生活も関係します。
前述の通り、食事をするとむし歯菌は酸を出します。酸が出る時間を短くする事が大切です。
ダラダラとご飯やおやつを食べていると、酸を出す時間が増え、歯に穴があきやすくなります。
●むし歯になりやすい時期があります。
むし歯になりやすい時期 ― それは、永久歯が生えたての頃です。
この時期は歯の質が弱いのです。成長するに従って歯も成熟して、強くなります。
6歳から20歳頃までにむし歯にならなければ、その後はむし歯になる可能性はグッと低くなります。
ですからこの時期に予防をしっかりしておくことが大事なのです。
●シーラント
上記の通り、生えたての永久歯はむし歯になりやすいのです。
むし歯になりやすい奥歯の溝を”シーラント”という薬品で埋めることで、むし歯になる確率はぐんと低くなります。
●フッ素を利用する
歯医者に定期的にフッ素塗布に来ることはもちろん効果的ですが、
お家でもフッ素洗口や家庭用フッ素ジェルを使用することで、さらにむし歯を予防することができます。
フッ素については ![]() 予防歯科をご覧ください。
予防歯科をご覧ください。
本当に怖い歯周病 
本当に怖い歯周病
"歯周病"という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
昔は"歯槽膿漏(しそうのうろう)"と呼ばれていたので、こちらのほうが聞き覚えがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。
●歯周病とは?
歯周病とは、歯の周囲に付着したプラーク(歯垢)が歯と歯肉の隙間に入り込み、歯を支えている骨を溶かしてしまう病気です。
プラークにはたくさんの歯周病菌が含まれていて、歯周病菌の出す毒素が歯ぐきに炎症を起こさせ、骨を溶かしてしまうのです。
骨が溶けてしまえば歯はグラグラし、いずれ抜けてしまいます。抜けたままにして放っておくと、歯周病菌は他の歯にも移り、骨を溶かし続けてしまいます。
また、歯周病は歯を失うだけでなく、心臓病や糖尿病などの全身疾患にも悪影響を与える事が、近年の研究で分かってきました。
成人の8割は歯周病を持つと言われているのですが、痛みがないため、気付かない方がほとんどです。
●歯周病の種類
歯周病は、歯肉炎と歯周炎の2つに分けることが出来ます。
●歯肉炎 ・・・プラーク(歯垢)が歯の周りに付着することで歯肉に炎症が起こります。
●歯周炎 ・・・歯肉炎が進行すると、歯を支えている骨に影響が出て、歯ぐきから血や膿が出たりします。
●歯周病を悪化させる要因
① 喫 煙 タバコを吸っている方は血流が悪くなりますので、歯周病が進みやすく、一度炎症が起きてしまうと治りづらいので、悪化しやすくなります。
② 糖 尿 病 身体の抵抗力が低下するため、歯周病も急速に悪化させてしまいます。
③ 女性の思春期、妊娠、更年期 女性ホルモンの影響で、歯肉に炎症を起こしやすくなります。
④ ス ト レ ス ストレスによる歯ぎしり、身体の抵抗力の低下によって、炎症を起こしやすくなります。
⑤ 口 呼 吸 口で呼吸をしていると、口の中が乾燥しやすくなり、炎症を起こしやすくなります。
⑥ 食 生 活 柔らかくて甘いものばかり食べていると、プラークができやすくなり、偏食をすると栄養摂取が不十分になり、抵抗力が低下します。
⑦ 歯並びが良くない 歯並びが良くないと、どうしても磨き残しが多くなり、プラークが付いたままの状態が続きます。
●歯周病の予防対策
歯周病は一度かかってしまうと、一生付き合わなければいけません。
ですから歯周病にならないよう予防することが、とても大事です。
・予防その1 プラークコントロール
歯周病菌はプラーク(歯垢)をエサにして繁殖します。しっかりとした歯磨きでプラークを付着させないことが大切です。
・予防その2 健康な食生活
柔らかいもの、糖分の多いものは出来るだけ避け、繊維質な野菜や果物などを食べることも予防効果があります。
・予防その3 生活習慣の改善
食生活以外にも運動、休養といったライフスタイルの改善も予防につながります。
・予防その4 定期健診に行く
健康な人なら1年に一度、歯周病になってしまった方は3~6ヶ月に一度の定期健診で、歯周病にならないように、なってしまった場合は悪化させないようにすることが大事です。
●歯周病チェック!
歯周病は歯ぐきの下で進行し、痛みもありませんから、自分自身ではなかなか気付くことが出来ません。
あなたが歯周病かどうか、チェックしてみましょう。
歯肉炎編
■ 歯肉に発赤・腫脹(赤く腫れること)がある。また、膿が出ることがある
■ 歯石が目立つ(歯の裏側がざらざらしている)
■ 口臭がする
■ 歯を磨くと出血する
■ 歯が浮いた感じや歯肉がしみたりする
歯周炎編
■ 歯肉炎の症状がある
■ 膿が出ていて、口の中が苦くなる(口臭も酷くなる)
■ 歯がグラグラ動く(物が噛みにくくなる)
■ ものを噛んだら、歯(根の奥深い部分)に痛みがある
いかがでしょうか?
もし上記に1つでもチェックが付いたら、歯医者に行くことをおすすめします。
気付いたら手遅れ・・・ということがない様に、定期健診にお越しください。
歯並びが悪くなるのはどうして? 
歯並びが悪くなるのはどうして?
歯並びの良い人もいれば、良くない人もいます。
では、歯並びはなぜ悪くなってしまうのでしょうか?
歯並びが悪くなる原因は、遺伝的な要因と後天的な要因によるものに分かれています。
この2つの要因がお互いに影響し合い、成長の中で徐々に、しかしハッキリと現れてきます。
まず、遺伝的な要因として
①歯の大きさ、形 ②歯の生える時期 ③骨の発育 が挙げられます。
次に、後天的な要因として
①乳歯のむし歯・脱落
…乳歯のむし歯を放って置くと、下にある永久歯に影響してしまいます。
②指しゃぶり・噛み癖・口呼吸などの癖
…指しゃぶりをしたり、なにげなく頬杖をついていることで、出っ歯になってしまったり、下あごが十分に育たなくなってしまう場合があります。
口呼吸も歯並びや顔面の発育に大きな影響を及ぼします。
遺伝的な要因を排除するのは難しいですが、
後天的な要因は、保護者ややお子さん自身が気を付けることで十分排除できます。
鼻呼吸、良い姿勢、噛む回数を多くすることで歯並びが悪くなるのを防ぎましょう。
それらは、矯正治療後の後戻りを防ぐためにも役立ちます。
■ 口呼吸から鼻呼吸にする!
口を閉じて、鼻で呼吸してみてください。
舌は口蓋(上アゴ)にくっついていますね。
次に、口で呼吸をしますと、舌が口蓋につきません。
身体というのは、面白いもので、舌が口蓋につかないと上アゴが狭くなろうと、歯を内側に動かしてしまうのです。上アゴが動けば下アゴも上アゴに合わせようとして動きます。
こうして歯並びは変化するのです。
舌の使い方や口呼吸から鼻呼吸へのトレーニング方法にMFTという方法があります。
当医院ではお口を閉じるトレーニンググッズとして「ポカンX」や「リットレメーター」、「とじろーくん」という器具をご紹介しています。
■ 良い姿勢で!
鼻呼吸ができても姿勢が悪いと、やはり舌が口蓋につきません。
猫背にしてみると舌が口蓋から離れていくのがわかると思います。 良い姿勢とは、深呼吸して息を吐き終わったときの姿勢です。
■ よく噛もう!
よく噛むことで口の周りの筋肉が成長します。
最近のお子さんはアゴが小さい、と言われますが、よく噛むとアゴも成長しますので、永久歯が生えるスペースが足りないということがなくなるのです。
1口30回を目指して噛みましょう。
「酸蝕歯(さんしょくし)」ってなに? 
「酸蝕歯(さんしょくし)」ってなに?
「酸蝕歯(さんしょくし)」とは、酸性の食べ物や飲み物(すっぱいもの)を食べることで「歯が溶けてしまった」「将来溶けてしまいそう」という歯のことをいいます。
●酸蝕歯になると…
エナメル質が溶け、象牙質が出てしまい、知覚過敏のような症状が出ます。
そしてエナメル質が溶けると、象牙質が透けて見えるので歯が黄色っぽく見えてしまいます。
また、歯が欠けたり、ひび割れたりします。
●いつもの習慣が酸蝕歯に…「え!?ウソ~!ダメなの!?」
![]() 『部活中、頻繁に、少量ずつスポーツ飲料を飲んでいる』
『部活中、頻繁に、少量ずつスポーツ飲料を飲んでいる』
脱水症状予防のために、水分をこまめに取ることはとても重要なことですが、飲み物が酸性の強いスポーツドリンクの場合、酸蝕歯になってしまうかもしれません。
こまめに飲むと、歯と酸との接触時間が増え、しかも部活となると毎日数時間にわたって飲むことになります。
特に中高生の場合、奥歯の永久歯はまだ生えたてで柔らかく、成人の歯に比べると溶けやすいので注意が必要です。
![]() 『毎日の運動後の水分補給にビタミンドリンクや黒酢ドリンクを飲んでいる』
『毎日の運動後の水分補給にビタミンドリンクや黒酢ドリンクを飲んでいる』
スポーツ後の水分補給に、黒酢ドリンクやビタミンドリンクを飲んでいる方もいらっしゃるでしょう。しかしそれらの飲み物は、身体には良くても、実は歯を溶かしやすい飲み物なので注意が必要です。
運動後はお口の中が乾いています。しかも汗をかいて体内の水分が減ると、唾液の分泌量も下がってしまいます。こうして唾液の力が弱まっている時に、習慣的に酸性の飲み物を飲むと、酸蝕歯になりやすくなります。
![]() 『赤ちゃんがぐずる時、哺乳瓶でジュースを飲ませると満足してよく寝てくれる』
『赤ちゃんがぐずる時、哺乳瓶でジュースを飲ませると満足してよく寝てくれる』
これがいけない事は、多くのママさん達がご存じではないかと思います。
赤ちゃんの生えたての乳歯は柔らかいので、酸性の飲み物にはとても弱いのです。
欲しがるたびに哺乳瓶やマグで果物のジュースを飲ませていると、酸蝕歯のリスクが大変高くなります。
ぐずる時に飲ませ、そのまま寝てしまうと、睡眠中は唾液量が減るので、口の中に酸が長く留まってしまいます。
![]() 『健康のために毎日グレープフルーツを食べ、その直後に歯みがきしている』
『健康のために毎日グレープフルーツを食べ、その直後に歯みがきしている』
柑橘系の果物は特に酸性度が高く、エナメル質を軟化させます。
食べた直後にゴシゴシ歯磨きをすると、エナメル質が過剰に削られてしまうのです。
![]() 『お酒はチューハイかワイン。チビチビ飲むのが好きで、おつまみはいらない』
『お酒はチューハイかワイン。チビチビ飲むのが好きで、おつまみはいらない』
柑橘系の果汁の入ったチューハイやワインをチビチビ飲むことで、歯が酸に触れる時間が長くなります。
さらにおつまみを食べないことで唾液の分泌量が減り、さらに酸蝕歯のリスクを高めてしまいます。
![]() 『コーラが大好きで毎日飲んでいる』
『コーラが大好きで毎日飲んでいる』
「コーラを飲むと骨が溶ける」なんていう都市伝説もありました。
私もコーラが大好きなのですが、実はコーラは市販の清涼飲料水の中でも、特に酸性の強い飲み物なのです。
大好きなコーラを毎日、そして少しずつ飲むことで、酸蝕歯のリスクが高まってしまいます。
●予防しよう!酸蝕歯
![]() 酸っぱいものを食べたら30分ほど歯みがきを控える
酸っぱいものを食べたら30分ほど歯みがきを控える
「食べたらすぐ歯磨き」を心掛けている方も多いと思います。食後の歯みがきは、むし歯を予防するためのとてもよい習慣です。
でもちょっと待ってください。
酸に触れて軟らかくなっている歯をゴシゴシと磨くと、エナメル質の表面が削れてしまうのです。
酸っぱいものを食べた後は、お茶を飲んだり、うがいをして、唾液の力で軟化がおさまる30分ほど後に歯を磨くと良いでしょう。
![]() 酸性の飲食物を口にしたら、その後すぐ水やお茶を飲む
酸性の飲食物を口にしたら、その後すぐ水やお茶を飲む
酸が口の中に長く残らないよう、水やお茶で口の中をすすぐつもりで飲むと良いでしょう。
健康のためにビタミンCドリンクや黒酢など飲んでいる方は、サプリメントに変えることで酸蝕歯を予防できます。
![]() フッ素入り歯磨き剤やジェルを使う
フッ素入り歯磨き剤やジェルを使う
フッ素入りの歯磨き剤やジェルを使用して、エナメル質をケアし、歯質を強くしましょう。
酸蝕歯予防専用の歯みがき剤も効果的です。
![]() 軟らかい歯ブラシを使う
軟らかい歯ブラシを使う
軟らかめの歯ブラシを使い、ゴシゴシ磨きを避けることで、酸蝕歯を予防できます。
また、歯ブラシの使い方は、癖がついていることも多く、同じ場所に磨き残しが出来る場合もあります。一度歯科医院でブラッシングのチェックをを受けるのも良いと思います。
![]() 赤ちゃんに哺乳瓶でジュースを飲む習慣をつけない
赤ちゃんに哺乳瓶でジュースを飲む習慣をつけない
赤ちゃんはジュースやイオン飲料が大好きですね。
しかし哺乳瓶でこうした飲み物を飲む習慣がつくと、生えたての乳歯は大きなダメージを受けてしまいます。
![]() 口が渇いている時は、酸性の飲み物を避ける
口が渇いている時は、酸性の飲み物を避ける
唾液が少ない時に酸性の飲み物を飲むと、酸蝕歯になりやすくなります。
口が渇いている時は、水やお茶で潤すと良いでしょう。
「酸蝕」という現象は、食事をしている限り、必ず起こっていることです。
歯を溶かしやすい食べ物や飲み物の中には、健康にいいものも沢山ありますので、必要に応じて食べたり、飲んだりすることは大事なことです。
「そういうものがある」ということを知ることが、予防への第一歩です。
「キーン!」・・・しみる!知覚過敏 
「キーン!」・・・しみる!知覚過敏
冷たいものを食べた時、歯がしみたことがあるでしょうか?
一瞬キーンと脳を突き抜けるような痛みが走る、それが知覚過敏です。
なぜ、知覚過敏になると、あんなに強烈にしみるのでしょうか?
それは歯を覆って守っているエナメル質のどこかが部分的に失われているからです。
エナメル質が失われたところは象牙質がむき出しになり、直接刺激が伝わってしまいます。
今では知覚過敏の原因が解明されたと同時に、露出した象牙質を保護するコーティング剤を塗ったり、レジンで埋めたりする方法で象牙質への刺激をシャットアウトすることが出来るようになっています。
辛い痛みを我慢せずに、一度ご相談ください。
Q. 歯がしみる原因は?
A.歯周病で歯ぐきが下がった
「なんだか前より歯が長くなったみたい」と感じたことはないでしょうか?
歯周病になって歯ぐきが退縮すると、歯が長く見えます。
歯の根元はセメント質で覆われていますが、エナメル質ほどの硬度はなく、強いブラッシングなどによって簡単に削れてしまいます。
A.ゴシゴシ磨きでエナメル質を削った
歯磨きはとても大切な習慣ですが、あまりにゴシゴシと強く磨いていると、エナメル質が削れてしまいます。
歯垢は強い力よりも、弱い力で磨いた方がキレイに落とせます。
また、歯ブラシが硬すぎる場合も、エナメル質が削れてしまいます。
A.すっぱい飲食物で酸蝕症でに
「身体に良い」とされる黒酢やグレープフルーツなどの酸を含んだ食品ですが、
頻繁に取り続けると、酸に溶けやすいエナメル質はだんだんと溶かされ、薄くなってしまいます。
A.歯磨き粉が・・・!
長い時間丁寧に歯みがきをするのは構いませんが、歯をきれいにしようと粗い研磨剤の入った歯磨き粉でむやみに磨くのはやめましょう。
「歯磨きには歯磨き粉を使うもの」と考えがちですが、
歯磨き粉を使用しなくても汚れは十分キレイに落ちます。
A.歯ぎしりで歯がすり減った
就寝中の歯ぎしりで、歯が磨り減ってしまいます。
奥歯が削れてしみたり、前歯の先が削れたり欠けたりしてしみるなどの症状が表れます。
A.歯ぎしりや噛みしめで、エナメル質にヒビが入った
過剰な力が歯の表面を覆っているエナメル質にかかると、細かいヒビが入ってはがれやすくなります。
歯ぎしりの激しい方は、ダメージを防ぐため、マウスピースを装着して就寝すると、歯に無理な力がかかりません。
Q. しみるとき、どうする?
A. ブラッシング エナメル質や歯ぐきを傷めないブラッシングの仕方があります。歯科衛生士にご相談ください。
A. 歯磨き粉 フッ素の配合された知覚過敏専用の歯磨き粉を使うといいでしょう。
A. 飲食 酸性度の強い飲食物は、エナメル質を溶かしやすいので、しみやすい方はなるべく酸性度の高い飲食物は控えましょう。
A. 治療 しみる症状がなかなか治らず辛い方への治療として、象牙質の表面を保護してしまう方法があります。
さらには、神経を抜くという治療もありますが、歯の寿命を縮めてしまうのでおすすめ出来ません。
知覚過敏を我慢せずに早めに治療することで、象牙質(第二象牙質)が形成され、象牙細管では石灰が沈着し刺激を感じにくくなっていきます。
口臭予防 
口臭予防
自分の口臭が気になることはありますか?もしくは人に指摘されて悩んだことはありますか?
口臭は一度気になり出すと、人と話しづらくなってしまったりもしますね。
口臭の原因は、内臓にある場合もありますが、85%は口の中にあります。
原因を知り、予防を身に付ければ、もう口臭に悩むことはありません。
●口臭の分類
<自臭症> 精神的ストレスなどで緊張してのどが渇いた時や、睡眠中の唾液低下による朝の起床時、また空腹時に起こる生理的口臭です。
<他臭症> 虫歯や歯垢・歯石が付いた時、歯周病などの時の病的口臭です。
Q. 口臭の原因は?
A. 食べ物
ニンニクやニラ、ネギなどのニオイの強いものを食べた場合は、これらが食後に口臭となって吐き出されます。
アルコールの場合は、アルコールが分解されて出る成分がニオイの元で、歯を磨いてもなかなか治まりません。しかし、これらの口臭は、時間とともに自然となくなります。
A. 全身の病気
全身の病気が原因で、口臭が起こることがあります。
これらの原因となる病気は様々で、それぞれの病巣によってニオイの種類が変わるのが特徴です。
たとえば、糖尿病にかかっている人が出す果物の傷んだようなニオイは特徴的で、口臭によって病気に気付くという場合もあります。
A. 口の中~プラーク(歯垢)
口臭の原因として最も多いのは、プラーク(歯垢)によるものです。歯垢はむし歯の原因になるものですが、口臭の原因にもなります。通常食後2時間ほど経つと、歯垢は分解されて、におい始めます。 歯垢による口臭を防ぐには、歯磨きが最も効果的です。
A. 舌苔(ぜったい)
舌に白い苔のようなものがつくことがありますが、これが舌苔とよばれるもので、歯の周りにつく歯垢と同じような成分で出来ています。これが口臭の原因となります。また、抗生物質などの薬の影響や糖尿病などの病気によっても、舌苔の量や色などが変化することがあります。
A. むし歯や歯周病
むし歯や歯周病がある場合は、さらに口臭がひどくなります。
このような状態を放置すると、通常の歯磨きでは歯垢が落としにくくなるため、さらに口臭も、むし歯や歯周病も悪くするという悪循環を繰り返してしまいます。
A. 唾液の減少
お口の中は、常に唾液がサラサラと流れて自浄作用が働いていますが、この唾液が少なくなった時に、口臭が強くなることがあります。
例として、朝起きた時、睡眠中に唾液が減少することでお口の中が渇き、粘膜の剥離(はくり)したものがたまって、口臭が強くなります。
●予防方法
◆ 口臭は、主にお口の中の病気が原因で発生しますが、そのほとんどが歯やお口の汚れと関係しています。
正しいプラークコントロールで、口臭も、むし歯や歯周病も予防できます。
◆ 舌苔の多い人は、舌専用のクリーナーでやさしくブラッシングしてください。 あまり強くこすってしまうと味蕾(みらい)が傷付き、味覚障害が起きてしまいますのでご注意ください。
また、はちみつを舌に塗ることで舌苔を除去できます。はちみつに含まれるグルコン酸と強い殺菌作用が菌の増殖を防いでくれます。100%のはちみつキャンディーをなめることでも効果があります。
◆ 入れ歯を使用している人は、食後に入れ歯を取り外して洗い、ご自分の歯も磨きましょう。 入れ歯は専用のブラシか歯ブラシでブラッシングしてください。歯磨き粉をつけると傷が付いてしまうので使用しないでください。
◆ ブリッジの部分は、ダミーの歯と歯ぐきの隙間を念入りにお掃除してください。
この部分はプラークが溜まりやすく、歯ブラシも届きにくいので、口臭や腫れの原因となってしまいます。歯間ブラシを使うときれいに取れます。
ドライマウス 
ドライマウス
ドライマウスとは唾液の減少などにより、口の中が乾く症状です。
原因は、ストレスや薬の副作用など多岐にわたります。
進行すると、口の中の渇きにより夜中に目を覚ましたり、食事が取りにくくなるなどの症状が見られます。
ドライマウスの症状
● 口の中が乾く・ネバネバする
○ 乾燥した食品を食べるのが困難
● しゃべりにくい
○ 口臭が強い
● 食事のとき舌が痛む
○ 味覚がおかしい
● 口が乾くので水をよく飲む
などが挙げられます。
ただし、上記の症状に当てはまるからと言って100%ドライマウスとは限りません。
シェーグレン症候群などの病気が原因でドライマウスになることもありますので、 早めの受診をおすすめします。
Q.ドライマウスの原因は?
A.食生活
現代の食生活は、ファストフードなどのように、唾液を十分に出さなくても飲み込めるような食事が主流になっており、唾液の分泌が従来よりも少なくなり、口が乾きやすくなっています。
A.精神的ストレス・緊張
「緊張してのどがカラカラ」という経験はありませんか?私はあります・・・。
ストレスがかかったり緊張すると、交感神経が刺激され、唾液の分泌が抑制されます。
A.薬物
抗うつ剤、鎮痛剤、抗パーキンソン剤、降圧剤などの多くの薬物の副作用として唾液分泌の低下があります。
A.加齢
年齢とともに口やあごの筋力低下や萎縮が起こり、唾液の分泌量が低下します。
A.口呼吸
鼻の疾患や癖などで、口で呼吸することにより、口が乾く原因となります。
A.病気
浮腫、脱水症、糖尿病、シェーグレン症候群、放射線、骨髄移植など。
ドライマウスの治療・ケア
◎ 水分補給
◎ 潤滑剤が配合された洗口剤の使用
◎ 口呼吸の改善
◎ 唾液分泌促進剤や漢方薬の服用
◎ 人工唾液の使用・・・エアゾール剤を使用し口腔内に噴霧。正常唾液に似た成分で作られており、不足している唾液の補充療法とされています。
◎ 口腔機能訓練
◎ 保湿装置の使用
◎ 生活習慣や体質の改善
◎ 口腔内洗浄、PMTC
◎ うがい液・トローチ・・・腔内を清潔に保ち、むし歯を予防する目的で使用されます。トローチには唾液の分泌を促進する効果もあります。
ドライマウスの方は、むし歯や歯周病になりやすいため、
定期健診により口腔内の清掃や洗浄を行い、ケアすることも大切です。
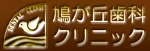
 HOME
HOME 地図・診療時間
地図・診療時間 スタッフのご紹介
スタッフのご紹介 院内のご案内
院内のご案内 メール
メール